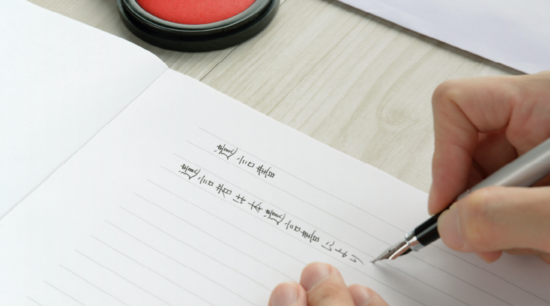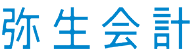新着情報
組織再編時には「行為計算否認規定」にご注意ください。No.952
戦う税理士の小栗です。
12月も半ばを過ぎ、今年も終わりだなと感じる季節になりました。
師走というくらいですから皆さんも忙しくされているだろうと思います。
当事務所では組織再編(合併、分割、株式交換、株式移転)といった
特殊な業務の依頼を受けることが良くあります。
例えば2社を合併させるといっても合併比率は如何するのか、
資産や事業の引継ぎはどうするのか、
今までに生じた赤字や剰余金はどうするのか、
など検討すべき課題は色々とあります。
また、適法に行われていれば「適格組織再編」として税務的に問題はなくとも、
まれに適法であっても行為計算否認規定(法法132の2)の適用を受けて認められないこともあります。
実際に「適格の要件を満たしているのにも関わらず、認められないケースとはどういったものなのか?」
といったご質問を受けることも多々あります。
ということで、今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは
「組織再編を行う時には「行為計算否認規定」にご注意ください」です。
さて、法律の要件を満たしているにも関わらず
認められないケースというのはどのような時なのでしょうか。
結論を申し上げると
「租税回避が目的だと思われる事例」であるという事になります。
この話は以前にも取り上げておりますので
ご記憶にある方もいるかと思いますが、
この根拠となる考え方が令和5年3月23日の裁決事例で示されています。
この事案は繰越赤字のある子会社2社の事業を新設の子会社に分割をした上で、
繰越赤字の残った会社を本体会社と合併させたという事例でした。
100%子会社の合併ですから、
いわゆる「適格合併」にあたり通常であれば何も問題はないケースです。
しかし課税当局側はこの合併には赤字を親会社に引き継がせるという目的以外には
合理性がないという事で否認をしています。
法律違反も何もないのに認められないなんてひどいという声が聞こえてきそうです。
こんな時に考えてみる必要があるのは、
課税当局はなぜ租税回避だと認定をしているのかという点です。
ここに根本的な根拠が隠されています。
裁決事例には次のような表現がされています。
・組織再編税制は実態にあった課税の観点で原則課税であるが、
資産移転の支配が続いている限りはその繰延を認めている
・被合併法人で営んでいた事業が合併法人で引続き営まれている
比較的簡単で当たり前のことを言っていますね。
では、今回の事例に当てはめてみましょう。
2社の事業は新会社に引き継がれている。
2社には赤字だけが残った。
その赤字会社を親会社が吸収合併した。
つまり、どちらの要件も満たしていないわけです。
他の形式要件をすべて満たしていたとしても
やはり認められないということですね。
では、合併した会社に何らかの事業が残っていたとしたら
否認はされなかったのでしょうか。
これはケースバイケースだとしか言いようがありませんが
少なくとも全く反論の余地なしとはならなかっただろうと私は思います。
ただでさえ複雑な組織再編税制ですから、
プランニングは慎重の上にも慎重にが基本です。
では、次回もお楽しみに。