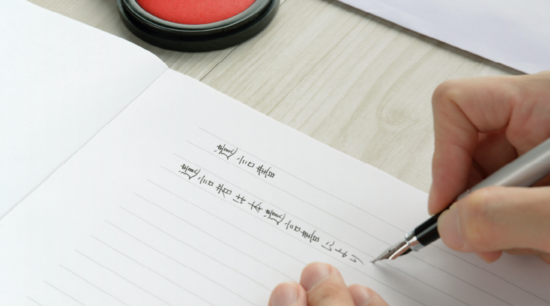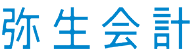新着情報
戦う税理士 小栗のメールマガジン
「イノベーション拠点税制に注目してみましょう」No.980
皆さん、こんにちは。戦う税理士の小栗です。
3月決算の会社は決算処理に追われているのではないでしょうか。
我々の事務所も上場をしている大きな会社から決算をまとめていかないといけませんから、
すでに戦場にいる状態です。
今年もGWは休めないのか・・・と憂鬱になる季節でもあります。
とはいえ、忙しくても企業経営に役立つ新しい税制はフォローをしないといけませんから、
今日はそんな情報です。
ということで、
今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは
「イノベーション拠点税制に注目してみましょう。」です。
皆さんは令和6年度税制改正で創設された「イノベーション拠点税制」についてご存じでしょうか。
この税制は、研究開発拠点としての競争力を強化し、
無形資産への民間企業の投資を後押しする目的で設けられたものです。
本年4月1日から施行され、特許権やAI関連プログラムの著作物(以下「対象知的財産」)
に基づく所得に減税措置を適用することが可能となりました。
3月27日に経済産業省が公表した「イノベーションボックス税制ガイドライン」(全91頁)では、
制度の詳細や計算方法、手続きについて具体例を交えながら解説されています。
この制度では、対象知的財産に関連するライセンス取引や譲渡取引から生じる所得に対して
30%相当額を所得控除することが認められます(関連者との取引は対象外)。
対象は青色申告を行う法人で、企業規模や業種に制限はありませんからどの企業にも該当します。
では、対象となる「特許権」や「AI関連プログラムの著作物」にはどんなものが含まれるのでしょうか?
具体的には、研究開発の成果として令和6年4月1日以降に取得・制作された知的財産が対象です。
AI関連技術を活用したプログラムが該当し、
例えばユーザインターフェースの改良のみを行ったプログラムは対象外となります。
対象か否かの判定は、ソフトウエア協会などの第三者による証明が必要です。
さらに、所得控除の適用を受けるには「自己創出比率」の計算が必須です。
これは、対象知的財産に直接関連する研究開発費の割合を算出するもので、
国内で行った研究開発費用が中心となります。
計算方法や経過措置もガイドラインに詳しく記載されていますが、
令和8年度までは企業全体の研究開発費を基準に計算できる緩和措置が取られています。
また、税制適用には経済産業省の証明書が必要です。
申請期間は事業年度末日から前後30~60日間で、審査後に交付されます。
税務申告の際には、この証明書を添付する必要があります。
本制度は、今後の研究開発を大きく後押しするポテンシャルを秘めていますが、
活用には専門的な知見が欠かせません。
対象要件や手続きについて十分に確認し、適切な対応を進めていきましょう。
特にAI関連技術を活用したプログラム開発に注力している企業にとっては、
非常に有効な制度と言えるでしょう。
私もまだまだ勉強不足ですが、「イノベーションボックス税制ガイドライン」を読み込んでみます。
では、次回もお楽しみに。
↓前回のメルマガはこちら↓